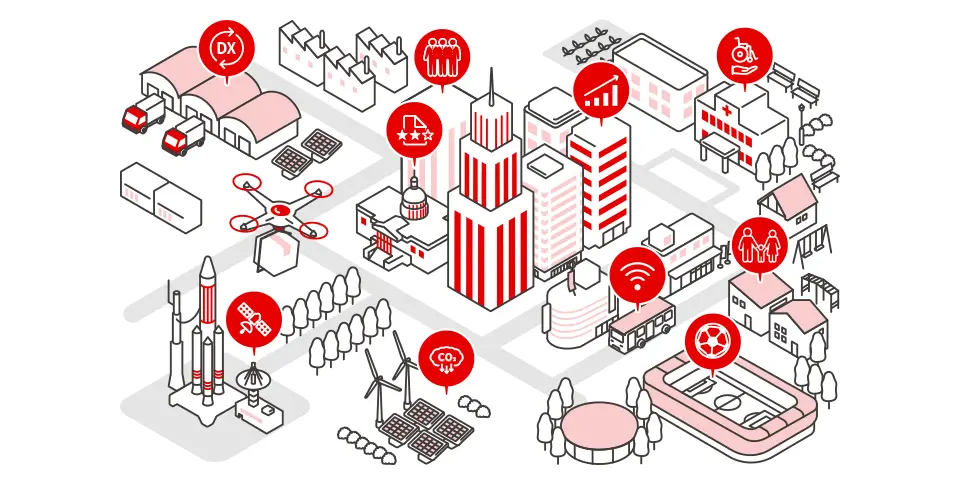テーマから見るMURCの最前線
新技術の社会実装


都市で育むイノベーションの現場

政策研究事業本部 東京本部 経済財政政策部
2019年入社/融合理工学府 修了
学生時代は都市計画を専攻し、脱炭素型の都市づくりについて研究。入社後は都市・エネルギー政策に係る調査研究や新技術の社会実装に係る実証実験支援等のプロジェクトに参画し、自身のミッションである「災害に強い都市づくり」の実現に向けた研究を進める。
Q1 背景や課題は?
新たな技術。街で試す、その第一歩
日本の都市では、気候変動による災害の激甚化・頻発化、そして災害時のエネルギー確保に対する不安等、従来の仕組みだけでは対応が難しい複雑な課題が表面化しています。こうした社会的変化に対応するには、単なるインフラ更新にとどまらず、新しい技術やサービスをどのように都市に根づかせていくかが問われています。
新たな技術を開発する企業等では、着想からプロトタイプ開発、そして事業化に至るまでの過程をいくつかの段階に分け、各フェーズで技術の有効性や社会的受容性を見極めていくことが重要です。
この過程で欠かせないのが、実際の都市空間を使った実証実験です。しかし、実証にあたっては、資金調達やフィールドの確保、関係者との調整といった多くの負担が発生します。さらに、適切な仮説設計がされていなければ、十分な成果が得られないという懸念もあります。
特に、初期段階にある研究開発は不確実性が高く、民間からの十分な支援を得るのが難しい場合も少なくありません。そのため、行政機関が実証実験を支援する役割は今後ますます重要になると考えられます。
Q2 アプローチの方法は?
実証の場づくりを通じて、企業と地域をつなぐ
これまでの受託業務では、AI・IoT等の先端技術を活用して新たな製品やサービスの事業化を目指す企業と、それらを活かして社会課題の解決やイノベーションの創出を図る自治体との橋渡し役として、実社会における実証実験の場の設計・支援に携わってきました。
具体的には、自治体が重視する社会課題や重点分野に即したテーマ設定を行い、それに沿った実証提案が集まるような事業の企画を検討。また、実証の機会を求める企業に対して情報を発信し、実証フィールドとのマッチングや調整、各種サポートも行っています。
さらに、実証実験が次の開発フェーズへの移行につながるよう、必要な検証項目の整理や計画への助言、実施中の進捗管理といった伴走支援も行い、より実効性のある実証実験となるよう心がけています。
こうした支援においては、単なる先端技術の実用化にとどまらず、その成果が社会課題の解決や地域への展開につながるよう、産業振興と社会政策の両面を意識しながら取り組んでいます。

Q3 乗り越えるべき壁は?
技術のシーズと地域のニーズ。
両者のギャップを超えて
このテーマにおいて乗り越えるべき壁は、技術開発側と実社会側の視点の違いから生じるギャップです。
企業等は「何ができるか」という技術的可能性(シーズ)から出発することが多い一方で、行政や地域社会は「何が必要か」という課題解決の要望(ニーズ)を重視しており、両者の接点を丁寧に設計しなければ技術開発も実証実験も頓挫してしまう恐れがあります。
また、実証実験の実施自体が目的となってしまったり、支援内容が形骸化してしまったりすることで、その先の事業化や社会実装に結びつかないということも起こり得ます。
こうした事態を避けるためには、実際の地域社会の現場としっかり向き合い、次の展開や将来の社会の潮流を見据えた支援が欠かせません。社会政策的な視点と産業的な視点を行き来しながら、バランスよく両立させていくことが、この領域における実践の難しさであり、同時に私たちシンクタンクが果たすべき重要な役割だと考えています。
Q4 どんな未来を思い描く?
災害発生時も、いつもの生活をいつも通りに
これまで携わってきた技術の社会実装に関するプロジェクトでは、中小企業のDX推進や移動・業務の効率化といった社会課題をテーマに、関連する技術領域を手掛ける企業の伴走支援を行ってきました。
今後は、これまでの経験やノウハウを活かしながら、都市やエネルギーのレジリエンス向上といった視点での新技術の社会実装を手掛けていきたいと考えています。特に、災害時でもエネルギーを自給自足できるような技術や、そもそも必要なエネルギー量を減らすための技術を普及・高度化していくための支援はもちろんのこと、これまでにないエネルギー自立のあり方を模索し、そのための技術の発展や実装に貢献できたらと考えています。さらには、技術による便益が個人や企業単位にとどまらず、面としての広がりを持つ街や都市空間に広げていくような取組を行っていくことが目標です。
そうすることで、災害発生時においてもあらゆる人・企業がいつもの生活をいつも通りに過ごせるようになる。そんな社会の実現が理想です。
Frontier Index

成長戦略・新規事業戦略

人的資本経営
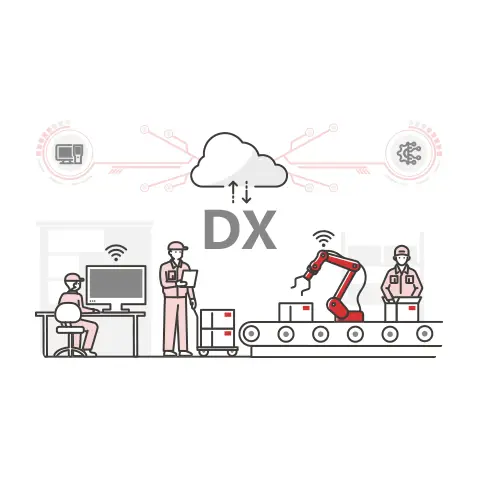
業務改革・DX
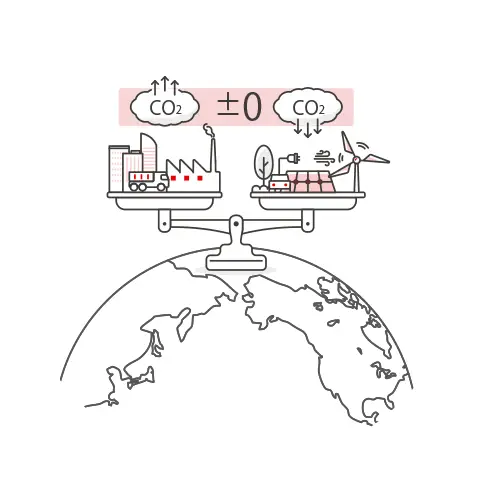
気候変動

都市・地域開発

EBPM・政策評価

新技術の社会実装

地域包括ケア・介護

子ども・子育て