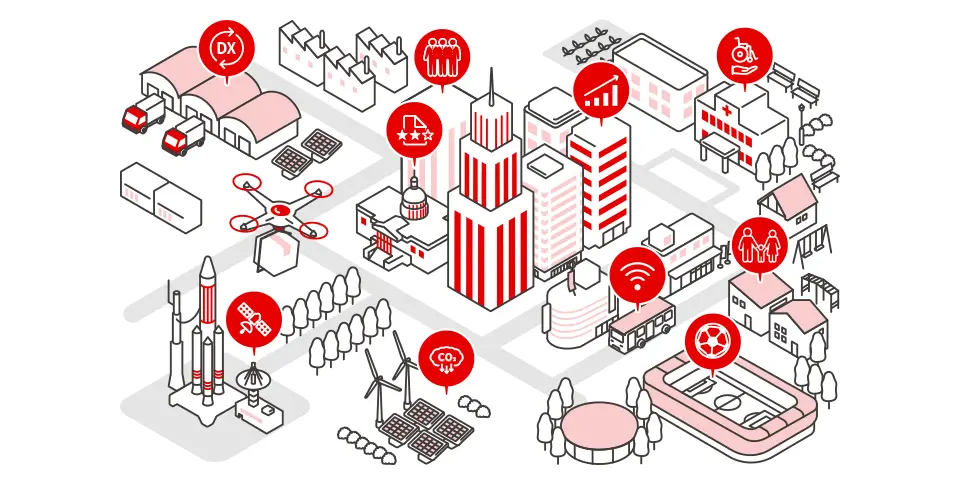テーマから見るMURCの最前線
人的資本経営


未来を見据えた人材戦略のあり方

コンサルティング事業本部
組織人事ビジネスユニット HR第3部
2020年入社/法学部 卒業
日系大手企業のクライアントを中心に、人材戦略策定・開示に関する支援を多数経験。その他にも、人事制度改定、定年延長、エンゲージメントサーベイ、組織風土改革等、人・組織に関するコンサルティング業務に幅広く従事している。
Q1 背景や課題は?
一貫性のあるストーリーを描く
人的資本経営は「人材を『資本』として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方」と定義されています。
近年、グローバル化やデジタル技術の急速な進展により、企業の競争力の源泉として人材の重要性が一層高まり、人的資本経営の関心が高まっています。さらに、上場企業に対して有価証券報告書での人的資本経営に関する情報開示が義務づけられ、企業経営における人的資本の扱いは避けて通れないテーマとなっています。
人的資本経営を実現するには経営戦略と連動した人材戦略の策定が不可欠ですが、今後の事業推進に必要な組織像や人材像、具体的なスキル等が明確でないため、経営戦略と人材戦略の繋がりを明示することが困難な企業も多い状況です。
また、採用、育成、配置、評価といった個別施策が場当たり的に行われているケースも多く、経営戦略と人材戦略、個別施策等の関係性を一貫したストーリーとして描いたうえで、それぞれを実行していくことが課題となっています。
こうした課題を解決するため、経営の中核として人材戦略を位置付け、適切なプロセスを実行しながら策定していくことが重要です。
Q2 アプローチの方法は?
三つのステップで人材戦略を策定する
課題を解決するためには、三つのステップで人材戦略を策定することが有効です。
ステップ1. As-Is(現状)の把握
経営と人事の両面から現状を立体的にとらえることが重要で、経営面では業績や事業環境、競争優位性等を、人事面では組織風土や社員の価値観、人材マネジメントの方針と施策の有無、実行状況等を可視化します。特に、経営状況の把握では人事部門だけで完結せず、経営企画部門等の関連部門との対話を通じて、正確な現状認識を行うことが重要です。
ステップ2. To-Be(あるべき姿)の具体化
経営戦略を実現するうえで、「どのような人材」が「どの程度」必要か等を明確に定義します。例えば、新規事業の強化が経営戦略に含まれている場合、既存人材とは異なるスキルや経験を持つ人材が求められる可能性があります。この段階で必要な人材の質と量を具体化することで、人材戦略と経営戦略の連動性を担保できます。
ステップ3. 人材戦略の方向性の策定・合意
現状と理想像のギャップに基づく重点テーマを踏まえて必要となる施策を検討することで、一貫したストーリーのもとで人材戦略を策定することができます。

Q3 乗り越えるべき壁は?
部門の垣根を越える。
データを整備・活用する
日本企業が人的資本経営を推進・高度化していくうえで乗り越えるべき壁は大きく二つあります。
ひとつ目は「部門の垣根を越えた検討体制の構築」です。人的資本経営を実現するには経営と人事が密接に連携することが不可欠です。しかし、実際は経営層と人事部門が共同で議論する場や体制が整備されておらず、人材戦略が現場任せになっている企業も多く見られます。人材戦略策定のみならず、施策の進捗を定期的にモニタリングし、柔軟に見直せる体制づくりが求められます。
二つ目は「人事データの整備・活用」です。人的資本経営では現状(As-Is)とあるべき姿(To-Be)のギャップを把握し、そこに向けた施策を計画・実行していくことが基本となりますが、その前提として信頼性の高い人事データ(個人の保有するスキルデータ、エンゲージメント関連データ等)が整備されていることが必要です。
実際にはデータが部門ごとに分散しており、どこに何があるのか明確でない企業も多く、施策のKPIの設定やPDCAの実行に支障をきたしています。今後はタレントマネジメントシステム等によりデータを一元管理し、戦略的に活用できる基盤を整備することが求められます。
Q4 どんな未来を思い描く?
企業とステークホルダーが
相互に高め合える関係を
前述のポイントを押さえた人材戦略を策定し、それをステークホルダーに開示することで「企業とステークホルダー間の建設的な対話が活性化されている状態」を理想としています。
例えば、投資家は「策定された人材戦略によって企業価値が向上するのか」に関心を持ちます。企業がこの問いに対し、経営戦略と人材戦略の連動性や成果への道筋を明示することで、投資家の納得感を高め、投資判断の一助となります。
さらに、対話を通じて投資家からの改善提案を受け、それをもとに人材戦略をブラッシュアップするような循環が生まれることも期待されます。
また、従業員や求職者にとっては「どのような仕事や成長機会があるのか」といった情報が重要です。
“就社”の概念が薄れ、企業が「選ばれる」時代において、自社ならではの魅力的な経験やスキルの獲得機会を具体的に示し、開示していく必要があります。その結果として、従業員が自発的に価値創造へ参画し、組織と個人が相互に高め合える関係の実現を目指しています。
Frontier Index

成長戦略・新規事業戦略

人的資本経営
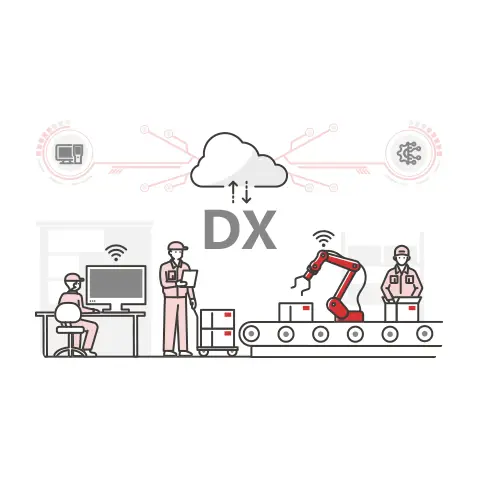
業務改革・DX
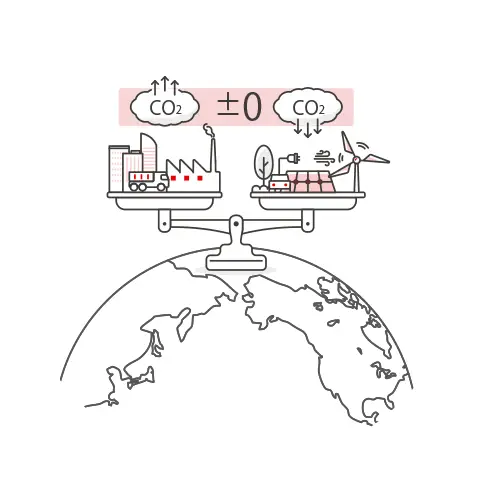
気候変動

都市・地域開発

EBPM・政策評価

新技術の社会実装

地域包括ケア・介護

子ども・子育て