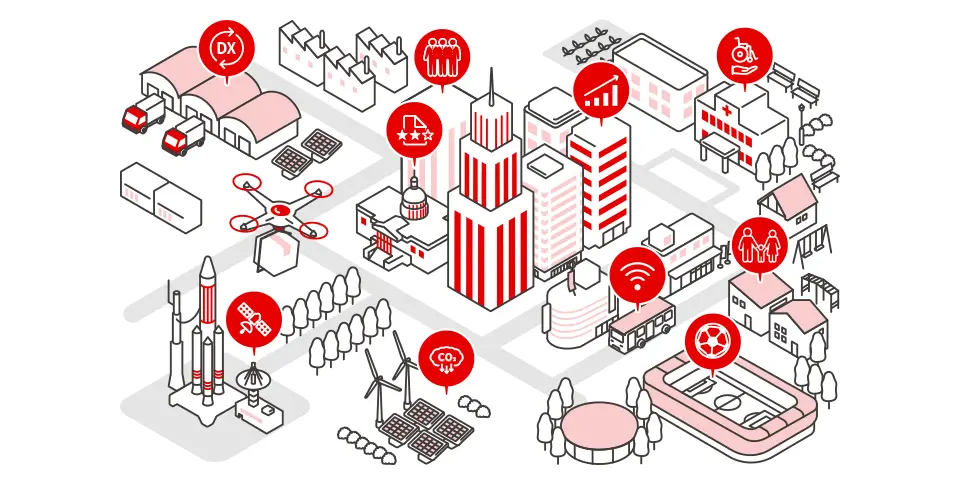社員インタビュー

地域の声を未来へとつないでいく。
沖縄・宮古島市で見つけた自分のミッション
副主任研究員/2013年入社/Master of Environment 修了
キャリアパス
地域における農林水産業の振興や、地域に経済還元がされる販路開拓について、調査や事業支援(人材育成)等に従事。
大学で専門としていた食品ロス関連の案件に関わる。都市農業の振興等にも携わり、地域の暮らしと地域産業の共存や、市民への政策の伝え方について関心が高まる。
農福連携の事業に携わる。リーダーとして独り立ちした時期で、キャリアの節目となる。
宮古島市のSDGs推進プラットフォーム(千年プラットフォーム)の組織化支援事業に携わる。
宮古島市に出向。2年半をかけSDGs推進プラットフォーム(千年プラットフォーム)の立ち上げに携わる。
自ら手を挙げ宮古島市に出向。
持続可能な島づくりへ
「多くの人々の役に立てる仕事はなんだろう」
小学生のころ、将来について考える機会があり、そのとき「環境に関わる仕事」がしたいと思いました。それからはずっと環境分野に関心を持ち続け、大学では環境学を専攻。
当社に入社してからは、「食や農業を通じた地域活性化」や「地域の持続可能性」等、環境とも関わりの深いテーマに取り組んできました。担当してきた地域は、東北や北陸、沖縄等多岐にわたりますが、それぞれの地域には独自の魅力がある一方で、抱える課題も異なることを実感しています。各地域に住む方々が、「この土地に暮らせて幸せ」と誇りに感じられるにはどうしたらいいか、そのために、自分にできることは何かを考えながら、仕事に向き合うようになりました。
入社7年目の2019年、環境省の事業として、沖縄県宮古島市におけるSDGs推進プラットフォームの立ち上げ支援に携わりました。宮古島市が掲げるエコアイランド宮古島=「持続可能な島づくり」の取り組をより強化するために、民間企業や行政が協力して新たなプロジェクトを生み出すことを支援するための仕組みです。
しかし、環境省による活動支援が2021年で終了する見込みとなり、宮古島市と三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、MURC)は、それまでの取り組みをどう継続していくかを模索することになりました。検討の結果、MURCが企業版ふるさと納税の制度を活用し、寄付および人材を派遣する形で支援を続けることになったのです。それならば、私自身が現地に移り住み、全力でこの取り組みに向き合いたい。そう考え2022年10月から宮古島市に出向することになりました。

相手の言葉に寄り添い、
伝えるべきことを「翻訳」する
宮古島市では、地域の持続可能性を高めるための事業を生み出し、課題の分析や提言ができる仕組みや組織づくりを目指していました。その実現には、ローカルシンクタンクとしての機能が求められます。しかし、こうした取り組みは国内でも珍しく、市内だけでは十分な知見を得るのが難しい状況でした。行政の方々もその必要性は感じていたものの、日々の業務に追われ、十分に手が回らない現実がありました。
そこで私は、宮古島市役所の一員として現地に入り、東京のメンバーと連携しながら、できる限りの組織化支援を行いました。現地では、行政関係者だけでなく、地元産業に携わる方々や地域の団体・自治会長等、さまざまな人たちと対話を重ねました。宮古島市に限らず、地域が抱える課題は多分野にまたがり、複雑に絡み合っています。たとえば農業ひとつをとっても、土地、生産、流通、加工、飲食、観光等、広い範囲に影響が及びます。
そうした多様な分野を横断的に調査・分析し、事例をもとに提案できるのは、シンクタンクならではの強みです。しかし、分野も立場も異なる人々は、それぞれ異なる「言葉」で語っています。俯瞰的な視点から一方的に伝えるだけでは、真の意味でのコミュニケーションにはなりません。それぞれの背景を理解し、相手の言葉を受け止めながら、伝えるべきことを丁寧に把握し、他者が理解しやすいよう資料化する等「翻訳」すること。これこそが、シンクタンクの研究員として本当に大切な役割なのだと、宮古島市での2年半の経験を通じて実感しました。

「そこに人の暮らしがある」
その当たり前を忘れないように
プラットフォームの組織化は、最終的に一般社団法人の立ち上げという形で実現しました。出向が終了した現在も、私はその社団法人の理事を兼任しており、東京と宮古島を行き来しながら活動を続けています。地域の方々から事業支援のご相談をいただく機会も増え、持続可能な島づくりへの一歩をともに踏み出せたことを嬉しく思います。
実際に宮古島市で暮らし、生活者のひとりとして地域と向き合った経験は、これからの仕事に大きく活きてくると感じています。地域が抱える課題は千差万別です。たとえば、オーバーツーリズムのように、経済的には成果が出ていても、住民の暮らしには負担がかかっているケースもあります。また、国が想定する地域課題と、地域の人々が目の前で感じている課題には、しばしばギャップが存在します。だからこそ、「そこに人の暮らしがある」という当たり前の視点を忘れないことが、全体最適だけに偏らない政策提言や社会実装つながる鍵となるはずです。
先ほど述べた「翻訳」という役割は、地域から国や行政に向けて声を届ける場面でも重要です。地域の人たちが守りたいもの、目指す未来、まだ言語化されていない魅力等を丁寧にすくい上げ、客観的なデータと重ね合わせながら言葉にしていく。それがシンクタンクの大切な役割だと実感しています。
日本各地で、こうした取り組みを積み重ねていくこと。それが、私にとってのミッションであり、ライフワークになっていくだろうと考えています。

入社の理由
大学では環境学を専攻していました。環境学では食品ロスや資源循環等、3Rや廃棄物に関わる研究をしていましたが、就職してからは生産や消費等、より上流からアプローチできる仕事に携わりたいと考えていたのです。シンクタンクに絞っていくつか選考を受けたなかで、MURCは社風や業務内容をはじめ、公開されている先輩研究員のレポートの内容も自分の価値観と合致していたため、「この人たちと仕事をしてみたい」と思い、入社を決めました。
MURCの良い点
研究員それぞれに専門分野があり、知的好奇心を持って仕事に取り組んでいます。政策や地域課題に対する熱量も高く、宮古島市で取り組んでいる活動についても、皆とても興味深く話を聞いてくれます。さまざまな経験や価値観を持つ方々とフラットに話せる環境にあることが、私の心の支えになっています。また、宮古島市で社会実装に取り組みたいという希望を受け入れてもらえたところに、自己実現やチャレンジを後押しする風土も感じています。
ある一日の流れ
メールチェック、今日明日のスケジュール再チェック
社内MTG
資料作成、クライアントへ連絡
休憩・移動
ヒアリング調査
移動中メールチェック
資料作成
退社
休日の過ごし方

宮古島市内で休日を過ごすときは地域のイベントに参加したり、友人とお店を開拓したりしています。何気ない会話から、地域の課題が見えてくることも。地域の食材を買って家で料理を楽しむ等、リラックスして過ごしています。
Interview Index

澤田 光晴
コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット
HR第2部
コンサルタント/2020年入社

溝川 翼
コンサルティング事業本部 社会共創ビジネスユニット
イノベーション&インキュベーション部
シニアマネージャー/2018年入社

吉野 英知
コンサルティング事業本部 経営戦略ビジネスユニット
経営戦略第2部
シニアマネージャー/2008年入社

大熊 丈士
政策研究事業本部 東京本部 地域政策部
研究員/2022年入社

髙原 悠
政策研究事業本部 東京本部 持続社会部
副主任研究員/2013年入社

仲嶋 翼
政策研究事業本部 東京本部 地球環境部
主任研究員/2015年入社