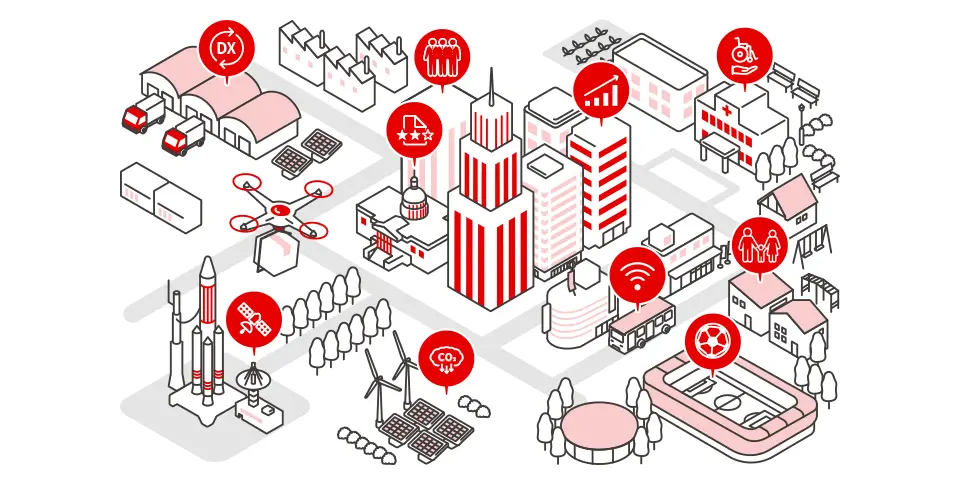社員インタビュー

データ分析で公共政策をより適切な形へ。
先端技術を手段にリアルな社会に貢献する
研究員/2022年入社/経済学部 卒業
キャリアパス
システム案件を中心に官公庁案件におけるデータ処理の基本を業務のなかで習得。
データ分析業務に多く従事。統計の基準改訂の業務を一部担当し、分析結果を顧客に説明する等、顧客接点を持つ機会も増える。
労働関係の調査研究業務にてデータ集計・分析業務のパートのリーダーとなる。分析テーマの精緻化から報告書の執筆に至るまで流れを他のメンバーに依頼する等、ある程度の裁量を持って業務に従事。
官公庁が提示した仕様書に対し、自ら手を挙げて企画を立案。周囲の力を借りて提案書を練り上げる。
データ分析によって
政策の因果を追う
ある政策が効果を発揮したように見えるとき、本当にその政策が原因だったのか、それとも他の要因で自然と状況が好転していたのか。そうした問いに答えるために欠かせないのが、データによる検証です。事象の因果関係をデータ分析によって推定することを「統計的因果推論」と呼びます。私は学生時代にこの考え方を学び、さらに公共政策への興味から、シンクタンクでデータ分析に携わる道を選びました。
現在は10人ほどのチームで、政策へのデータの活用や、統計の改善等に取り組んでいます。ビッグデータ解析もそのひとつです。そもそも、政府や民間企業が保持するデータは、分析ができるような形式をしていないことも少なくありません。膨大なデータを分析できる形に処理し、分析結果をグラフで可視化する等して、誰でもデータ分析を実施できる環境を整える。その設計を行うのも、私たち研究員の仕事のひとつです。
また、正確なデータをいかに現場から収集するかも重要なポイントです。その意識を強く持つきっかけとなったのが、入社一年目に携わった、特定の就労困難者についての官公庁の調査研究事業でした。適切な就労支援を行うために、就労困難者の特性や抱える課題を把握するための調査であり、当社では行政記録情報データを用いたデータ分析と、就労困難者本人が回答するアンケート調査の支援を行いました。

リアルな現場から得られる
より深い視点
行政記録情報データには、就労困難者の年齢等の属性情報や前職の情報、支援プログラム受講有無といった情報が含まれています。しかし、本人がどのような思いを抱えているのかは、アンケートで聞いてみなければわかりません。プロジェクトでは有識者の会議体を設け、調査方針や具体的な実施方法等についてアドバイスを受けながら、行政記録とアンケートの双方の調査結果を紐付けた分析を行いました。
調査項目の設計にあたっては、実際に支援の現場を訪問し、就労困難者が置かれている環境の把握にも努めました。たとえば、就労困難者のなかには、周囲に就労をしているロールモデルとなる人がいないことでイメージが掴めなかったり、対人のコミュニケーションの際の癖が抜けず、うまく職場の人と付き合えない等、就労に戸惑うケースもあるといいます。データだけでは見えてこない現場のリアルに触れたことで、後の業務において政策を検討する際にも、より深い視点を持てるようになったと感じています。
また、このプロジェクトは「収集した大量のデータから、どのようなことが分析可能なのか知りたい」というクライアントからの要望もありました。検討を行うには、そもそも各データがどのように定義されているかを、正確に理解せねばなりません。そのため、クライアントに細部を確認する必要があったのですが、最初は学生時代の癖が抜けず、無意識に専門用語を多用してしまいました。相手は必ずしもデータについて明るいとは限りません。誰にでも伝わる言い方を模索し、先輩に指導を受けながら資料の表現を何度も見直しました。そうした試行錯誤を通じて、丁寧で伝わりやすいコミュニケーションの方法を身につけていきました。

データ活用の可能性と
丁寧な議論の大切さ
行政のデジタル化が進むなかで、さまざまな情報がデータとして蓄積されるようになってきました。民間企業においても、購買履歴やGPSデータ、求人情報、さらには衛星画像まで、多様な分野でビッグデータが活用され始めています。かつては、官公庁が大規模な実態把握を行うにはアンケート調査に頼るしかありませんでしたが、近年は調査手法の幅が広がりつつあります。この流れは今後さらに加速し、社会の状況をよりタイムリー・高解像度で把握できるようになると考えています。
データをうまく活用できれば、政策の効果や課題を早期に把握し、改善のサイクルを迅速に回していくことが可能になります。こうした変化に伴って、データ分析の規模や高度さも増しており、分析手法そのものも日々進化しています。
我々も進化に追いつく必要がありますが、その一方で、先輩方の仕事を間近で見ていると、あえてシンプルな手法を選び、丁寧に議論を組み立てている姿に気づかされます。政策の背景や現場の実情を踏まえたうえで、分析結果を誰にでも伝わる形で提示し、地に足のついた議論を展開しているのです。
データ分析はあくまで手段にすぎません。最先端の技術を追い続ける姿勢を大切にしつつも、常にクライアントや現場の目線に立った分析を心がけたい。そうした姿勢で、政策形成に実質的な貢献ができる研究員を目指していきたいと考えています。

入社の理由
学生時代にコロナ禍を経験したことから、専門であるデータ分析スキルを公共政策に役立てたいという思いがありました。公的機関や政府系金融機関等を検討するなか、シンクタンクも候補にあり、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、MURC)のインターンシップに参加。若手とベテランがフラットにやり取りする姿に驚いたことを覚えています。最終的に、専門性を身に付ける働き方や、好奇心を軸としたキャリアが推奨される環境に魅力を感じ、入社を決めました。
MURCの良い点
ボトムアップな点だと思います。MURCでは、自分が関わる案件を上司が決めるのではなく、興味関心のある案件に自発的に参加することが基本です。ある程度経験を重ねれば、自分でプロジェクトチームを編成することもできます。研究員自身の好奇心、使命感、情熱といった内発的な動機を、最大限応援してくれる文化があると感じますね。自分は好奇心が先に立つタイプなので、関心のあるテーマにチャレンジできるこの環境がとてもありがたいです。
ある一日の流れ
自宅で勤務開始/メールチェック・返信
プロジェクト①の内部MTGに参加
プロジェクト②の外部協力先とのMTGを実施
出社・昼食
プロジェクト③の資料印刷等MTG準備
プロジェクト③のクライアント訪問。作業進捗を報告し、今後の作業方針を相談。
プロジェクト③のMTGを踏まえて、メンバーに作業依頼
プロジェクト①のデータ前処理を実施
退社
休日の過ごし方
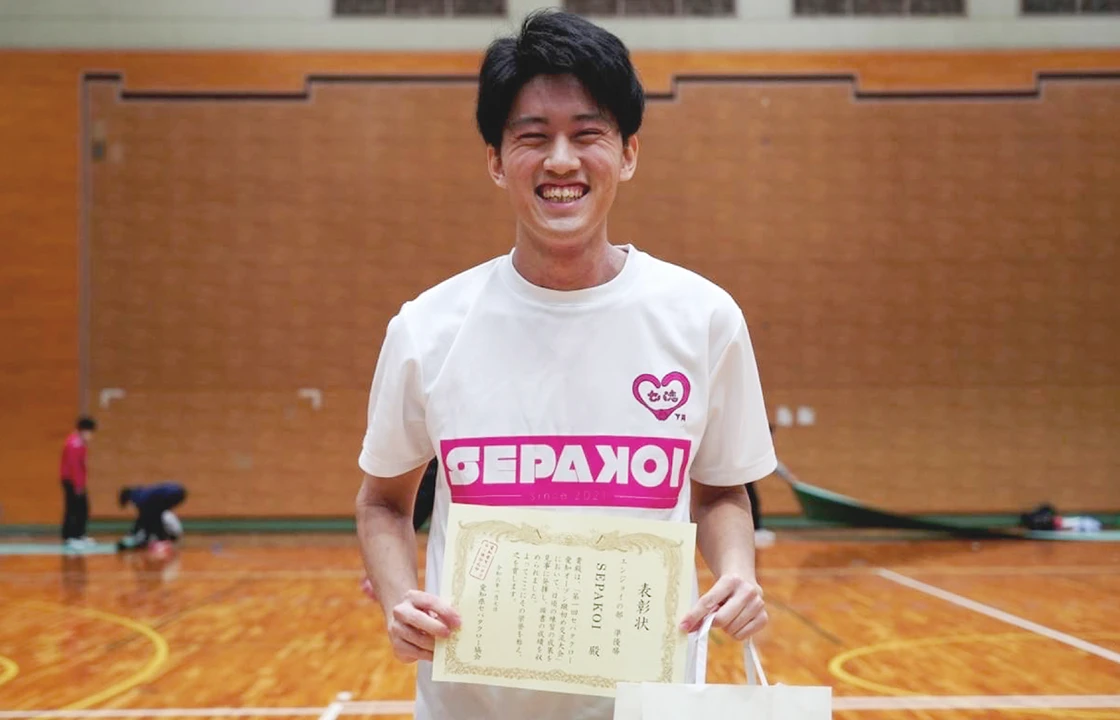
大学時代からセパタクローを続けています。3対3で戦うセパタクローは、チーム戦略の面白さに加え、個人技の影響も大きいのが魅力のひとつ。最近は大会の運営サポート等にも関わっています。
Interview Index

澤田 光晴
コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット
HR第2部
コンサルタント/2020年入社

溝川 翼
コンサルティング事業本部 社会共創ビジネスユニット
イノベーション&インキュベーション部
シニアマネージャー/2018年入社

吉野 英知
コンサルティング事業本部 経営戦略ビジネスユニット
経営戦略第2部
シニアマネージャー/2008年入社

大熊 丈士
政策研究事業本部 東京本部 地域政策部
研究員/2022年入社

髙原 悠
政策研究事業本部 東京本部 持続社会部
副主任研究員/2013年入社

仲嶋 翼
政策研究事業本部 東京本部 地球環境部
主任研究員/2015年入社