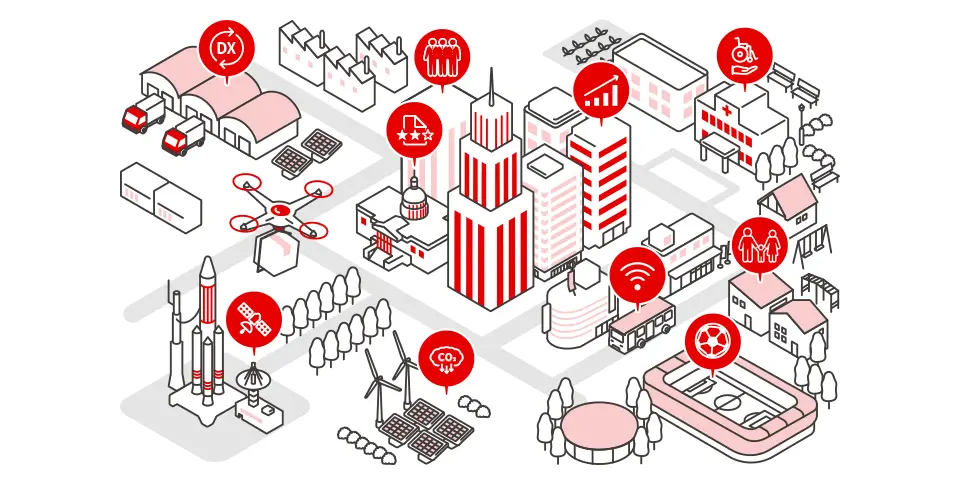社員インタビュー

人事課題解決の仕組みを考え体制を整える。
議論を重ね顧客とともに育てる生きた制度
HR第2部
コンサルタント/2020年入社/理学研究科 修了
キャリアパス
東京での集合研修の後、当時の名古屋ビジネスユニット組織人事戦略部、コーポレートアドバイザリー部の2部署にてOJTローテーションを経験。
組織人事ビジネスユニットHR第2部(名古屋)へ本配属。以降、基幹人事制度設計から退職金や再雇用制度の設計、定年延長、統合人事制度構築等、幅広いテーマに従事。
企業の根幹をなす
基幹人事制度の設計
組織人事ビジネスユニットにて、民間企業における人事領域の課題解決に携わっています。特に多いのが、基幹人事制度の改定に関する依頼です。
基幹人事制度とは、社内における格付けを能力や役割等に基づいて定義する仕組みである「等級制度」、会社の期待する役割や能力等の基準と個人の働きを照らし合わせて評価を行う仕組みである「評価制度」、そして会社への貢献に対する報酬として月例給や賞与を支払う仕組みである「報酬制度」の主に3つで構成される制度を指します。この基幹人事制度を中心として、退職金制度や再雇用制度等の、人材マネジメントを構成する仕組みが複数存在しています。
基幹人事制度は、基本的にほとんどの企業ですでに整備されています。そのうえで、ご相談いただく内容としては「今の人事制度が古く、会社として今後目指す方向にそぐわなくなってきた」というケースが大多数です。具体的には、変化の激しい経営環境のなかで、年功序列を前提とした制度から、個人の成果やチャレンジを評価する仕組みへと転換を図りたいというニーズの高まりを感じます。
基幹人事制度の設計は着手から導入まで短くても1年から1年半ほどかけて、現場の声も聞きながら慎重に進めていきます。私は現在サブプロジェクトリーダーの立場で、他メンバーの中心になってクライアントとの折衝やプロジェクトの推進を行う役割を担うことも増え、平均して5〜6つのプロジェクトに並行して携わっています。

企業規模で変わる課題と
求められる柔軟さ
人事制度は設計して終わりではありません。人事部門だけでなく、すべての従業員に制度が浸透し、正しく運用されて初めて意味のあるものになります。
配属2年目で主担当となったプロジェクトでは、制度設計の前段階から深く関わりました。まずは、会社としてどのような人材を育てていきたいか、その「期待人材像」の明確化からスタート。各階層の社員を対象にワークショップを設計・実施し、会社のビジョンに対する認識や、求める人物像についてのディスカッションを行いました。こうして得られた現場の声をもとに制度を設計し、導入フェーズでは評価者向けの研修も担当。制度が現場に定着するまでの一連のプロセスを支援した結果、足かけ3年にわたって関連する諸制度の整備も任せていただくことになりました。
一方で、さまざまな企業と向き合うなかで、この仕事の難しさを感じる場面もあります。私はこれまで主に、名古屋地域に拠点を持つ中小企業を中心に人事課題解決のを支援してきました。こうした規模の企業では人事に特化した部門がなく、人事制度に精通した人材が十分に育っていないことも多く、こちらから制度のあるべき姿を具体的に提案し、意思決定をしていただくという進め方が基本的なスタイルになっていました。
しかし、近年関わった社員数1,000人超の中堅規模の企業でのプロジェクトでは、事情が異なりました。この規模ともなれば、クライアント側にも豊富な人事の知見を有した方々が多くおり、求められたのは「具体的な提案」ではなく「自社の状況を客観的に整理したうえで論点の洗い出しをしてほしい」という要件だったのです。他社の事例を踏まえながら、現状を俯瞰し、社内議論の素材となるような分析や情報の提供を期待されていました。
最初は戸惑いもありましたが、クライアントの状況に応じてコンサルティングスタイルを柔軟に切り替えることも、私たちの重要な役割だと実感しました。それ以来、人事業界の最新の動向にも常にアンテナを張り、社内外の知見を取り入れながら、より多様な企業に価値を届けられるよう、自身のスキル向上にも取り組むことをより意識するようになりました。

トレンドに流されず
本当の課題を見極める
人事の領域においても、トレンドのようなものがあります。最近は「定年延長」や「ジョブ型」という言葉を多く目にするようになりました。以前は会社からの期待に沿った育成を大前提として、全体統一された基準とした「”会社”最適」な制度が多い印象だったのですが、近年は一人ひとりの生き方・働き方に寄り添った「”個人”最適」な人事制度のニーズが高まっているように思います。人手不足が慢性化するなか、人材獲得の意味でも、キャリア志向やワークライフバランス等を考慮した制度は有効でしょう。
ただ私は、こうした世の中のトレンドや、クライアントの要望を鵜呑みにした人事制度設計は危険だと考えています。ジョブ型への転換を希望されるクライアントでも、じっくりお話を伺うと、別の制度が課題解決に有効である場合もよくあります。
会社の在り方は十人十色。トレンドに流されることなく、クライアントが抱える本当の課題を見つけ、その課題を解決する仕組みを考える。そして、その仕組みを継続的に活用できる体制を整えることが重要です。会社の目指す姿の実現につながる人事制度を設計するためにも、単なる提案に留まらず、議論を積み重ねて一緒に制度を育てていくような、息の長い関わり方ができればと考えています。

入社の理由
学生時代は生命理学を専攻し、カエルの卵細胞を研究対象としていました。同級生の多くがメーカーの技術職や研究職を志望するなか、自分は特定の業種にこだわらず、「個人として評価される仕事はなにか」を軸に就職活動をしていました。そこで知ったのが「自分が商品」ともいえるコンサルタント業界です。長く働き続けるには人間関係が重要だと思い、選考では人の良さを重視。3回の面接すべてが柔らかな雰囲気だった三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、MURC)に入社を決めました。
MURCの良い点
人材育成への意識が高いと思います。コンサルティング事業本部では、入社1年目は3ヵ月の集合研修を経て、4ヵ月ずつ2部署へOJTローテーションされるため、自身のキャリアを考えながら経験を積むことが可能です。また、働き方の自由度が高く、もちろん与えられた役割を果たすことは大前提ですが、裁量労働制やフルリモートでの勤務ができます。私が勤務する名古屋には中小企業が多く、経営者と距離が近い状態でプロジェクトを進められます。この仕事のそれも魅力のひとつだと捉えています。
ある一日の流れ
出社/メールチェック・返信
MTG資料の確認
A社顧客MTG(オンライン)。人事制度の改定方向性について議論
昼食
B社のご提案資料作成 (課題整理、課題解決ロードマップ策定)
サブプロジェクトリーダーを務めるC社プロジェクトでの資料確認
上記資料について作成したプロジェクトメンバーへ通話しながら直接フィードバック・追加依頼
D社のご提案資料作成(退職金制度の現状分析)
退社
休日の過ごし方

中学生からバスケットボールを続けています。現在も3つのチームに所属し、2~3ヵ月に1回は大会に出ています。平日の18時に仕事を切り上げて、練習に向かうこともあり、ストレス発散のいい機会にもなっています。
Interview Index

澤田 光晴
コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット
HR第2部
コンサルタント/2020年入社

溝川 翼
コンサルティング事業本部 社会共創ビジネスユニット
イノベーション&インキュベーション部
シニアマネージャー/2018年入社

吉野 英知
コンサルティング事業本部 経営戦略ビジネスユニット
経営戦略第2部
シニアマネージャー/2008年入社

大熊 丈士
政策研究事業本部 東京本部 地域政策部
研究員/2022年入社

髙原 悠
政策研究事業本部 東京本部 持続社会部
副主任研究員/2013年入社

仲嶋 翼
政策研究事業本部 東京本部 地球環境部
主任研究員/2015年入社