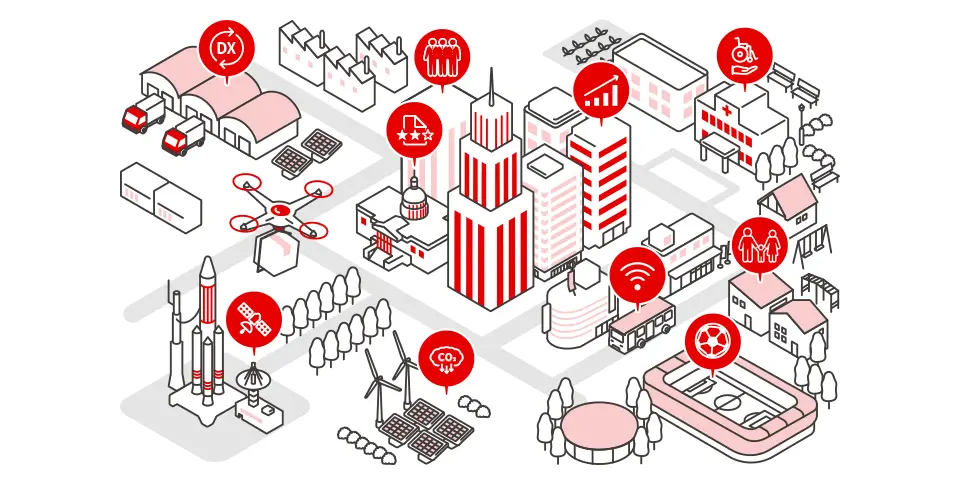社員インタビュー

技術と政策の双方を理解しているからこそ。
「自分だけの価値」で環境問題の解決と産業の発展に貢献する
主任研究員/2015年入社/情報科学研究科 修了
キャリアパス
政策研究事業本部に配属。大阪本部で地方創生や生物多様性、イノベーション創出等幅広いテーマに携わる。
東京本部で勤務。業務テーマを「プラスチック資源循環」と「バイオエコノミー」に絞り、中央省庁等の業務を担当。バイオ分野では自身がリーダーとして、業務開拓を進めている。
バイオテクノロジーの研究を経て
シンクタンクへ
学生時代はバイオテクノロジーを専攻し、大学院では、微生物を用いたバイオ燃料やバイオプラスチックの生産技術に関わる研究に取り組んでいました。研究者としての道もありましたが、先端技術を社会に広く普及させるための「仕組みづくり」に関心を抱くようになり、その思いからシンクタンクという進路を選びました。
入社後は大阪本部を経て、東京本部の地球環境部に所属し、「プラスチック資源循環」と「バイオエコノミー」をテーマとした中央省庁等の業務に携わっています。
プラスチック資源循環分野では、主にバイオプラスチックやリサイクルに関する技術を社会実装していくための政策づくりの支援や、企業や地域と連携した実証事業の支援等を行っています。バイオ分野では、より産業政策の色が強く、最新の研究開発動向の調査や、産業のエコシステム形成支援、標準化・ルール形成支援等も進めています。
大学院時代に身を置いた研究の世界では、特に博士課程において「オリジナリティのない仕事には価値がない」という厳しさを強く感じました。その経験もあり、いま自分が歩んでいる「技術と政策をつなぐキャリア」は、自分ならではのオリジナルを意識してつくっています。バリューを生み出すためにも、「自分にしかできない仕事」を意識しながら、日々の業務に取り組んでいます。

研究員に求められる
「研究者」と「サービスマン」の要素
国が推進するバイオ分野の取り組みのひとつに、「バイオものづくり」があります。微生物等の生物が持つ能力を活用して、燃料や素材、食品といった有用な化合物を作り出すもので、環境負荷が小さく、持続可能性の高い生産プロセスとして期待されているものです。
社会課題の解決には、特定の分野に閉じない横断的な視点が欠かせません。三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、MURC)には多様な専門性を持つメンバーが揃っており、プロジェクトごとに必要な研究員・コンサルタントと自由にチームを組むことができます。バイオ分野のプロジェクトでも、特定の地域産業やスタートアップ支援、知財等、それぞれに詳しいメンバーと連携し、総合シンクタンクとしての価値を提供できるように業務に取り組んでいます。
MURCでは、シンクタンクに所属する社員を「研究員」と呼びますが、私はこの研究員には二つの側面があると考えています。ひとつは「研究者」として、特定分野の専門性を深め、社会のあるべき姿を描けること。もうひとつは「サービスマン」として、目の前のクライアントの課題や悩みに真摯に向き合い、要望に沿った支援や提案を行えることです。
どちらが欠けても、本当の意味での「シンクタンク研究員」とは言えません。将来のビジョンを見据えながらも、求められているニーズを的確に言語化し、柔軟に対応していく。その両輪のバランスを常に意識しながら、日々の業務に取り組んでいます。

「自分にしかできない仕事」で、
バイオマス製品の普及を促す
プラスチックは基本的に石油を原料として作られています。一方で、国は2050年までに「ネット・ゼロ」(温室効果ガスの排出量と吸収・固定量の差し引きがゼロになる状態)を目指しており、その実現には、バイオマス製品への転換が不可欠です。
バイオマスプラスチックはすでに一部で実用化が進んできています。しかし、政策目標の実現にはさらに多くのプラスチックをバイオマス由来に置き換える必要があり、そのために安定供給やコスト面での課題等、多くの壁が立ちはだかっています。バイオマス製品がどの程度環境に良い影響をもたらすのかを定量的に評価していく取組も重要です。
こうした課題はプラスチックに限らず、バイオテクノロジーが浸透するさまざまな産業に共通しています。新たな技術が社会に普及するには、既存の社会システムを理解したうえでの事業のつくり込みや、新たなルールづくりが欠かせません。
そのようななかで、技術と政策の双方を理解している自分だからこそ、課題を整理し社会のデザインへ貢献するとともに、関連するプレーヤーの方をつないで事業をつくる「プロデューサー」のような役割が担えるのではないかと考えています。今後は、技術と政策に加え、経営への理解も一層深めながら、よりオリジナリティの高い仕事をする道を追求していきたいと考えています。

入社の理由
理系の博士課程にいたこともあり、最初は研究機関やメーカーの研究職への就職を考えていました。シンクタンクを選択肢に加えたのは、同業界出身の社会人ドクターとの出会いがきっかけです。その方の視野の広さ、見識の深さに惹かれ、「この人がいる業界ってどんなところだろう」と興味を持ちました。いくつかシンクタンクを受けたなかで、MURCの研究員は知の深さと心の熱さを併せ持つ方が多いと感じ、それが入社の決め手となりました。
MURCの良い点
仕事における「5W1H」の自由度が高いところに、MURCの良さを感じています。ある程度経験を積めば、誰とチームを組んで、どんな仕事をどのようにするか自分で決められるようになりますし、裁量労働制と在宅勤務によって、仕事をする時間や場所も選べるようになります。何のために仕事をするのかも、それぞれ胸に秘めたものがあるのです。年次によらず、互いを専門家としてリスペクトしあう雰囲気があるのも気に入っています。
ある一日の流れ
自宅でメールチェック・資料作成・オンラインMTG
家を出て会社に移動
出社し簡単に食事。MTG資料印刷。立ち話的に諸々相談
お客さまを訪問しMTG
退社
自宅でオンラインMTG
食事・家事・育児
自宅で資料作成・メール対応
終業
休日の過ごし方

学生時代から登山が趣味で、休日はたまに家の近くの山に登っています。いつでも山に登れるように、あえて都心ではなく山の近くに住んでいます。最近は子どもを背負って登ることも増えました。
Interview Index

澤田 光晴
コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット
HR第2部
コンサルタント/2020年入社

溝川 翼
コンサルティング事業本部 社会共創ビジネスユニット
イノベーション&インキュベーション部
シニアマネージャー/2018年入社

吉野 英知
コンサルティング事業本部 経営戦略ビジネスユニット
経営戦略第2部
シニアマネージャー/2008年入社

大熊 丈士
政策研究事業本部 東京本部 地域政策部
研究員/2022年入社

髙原 悠
政策研究事業本部 東京本部 持続社会部
副主任研究員/2013年入社

仲嶋 翼
政策研究事業本部 東京本部 地球環境部
主任研究員/2015年入社