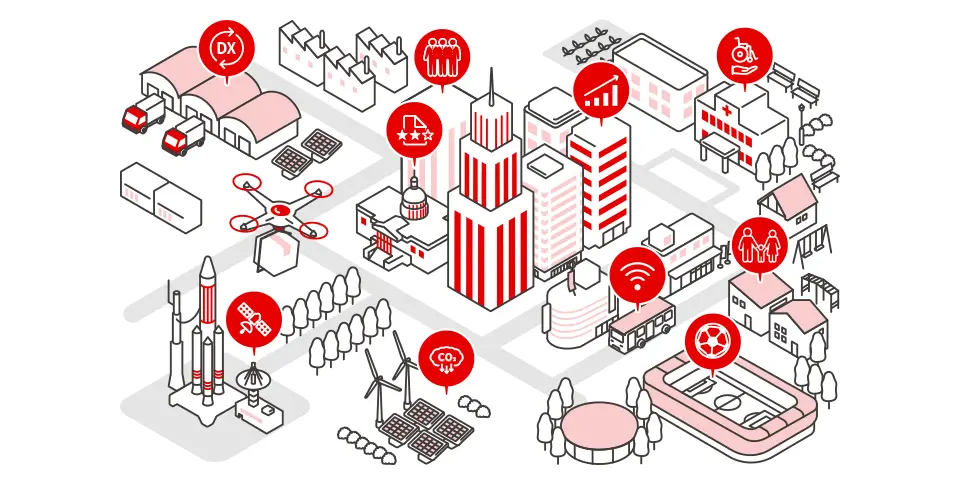キャリアの軌跡
政策研究事業本部 名古屋本部 研究開発第1部(名古屋)
副主任研究員/2017年入社/工学研究科 修了
専門領域:自治体支援・スマートシティ
新卒で入社以降、官民協働事業、公共施設計画、スマートシティ構想、DX推進等さまざまな自治体支援業務を通じて地域社会に携わる。各種調査やデータ分析、審議会等での合意形成支援を行い、地域がめざすべき方向性や必要な施策・取組の構築・目標設定等を行う。
入社理由
学生時代の研究で農林水産省の事業に携わっていたことから調査研究の立場から公的機関を支援することに関心を持つ。就職活動ではシンクタンク業界を志向し、最終的に身近な地域社会に貢献したい思いから、出身地である中部地方の自治体に対して豊富な支援実績のあるMURC(*)へ入社。
*MURC…三菱UFJリサーチ&コンサルティング準研究員
自治体の課題に挑む
入社1年目に市内の観光施設リニューアルに関する経済効果分析や年間の入場料収入や管理運営費等の事業収支計画を検討する案件に参画し、事業収支のシミュレーションを担当。定量的な分析は学生時代の得意分野でもあったが、これまでお金の計算に関してはほとんど経験がなく、また計算結果等が市の議会資料等にも活用されるといったことの重大さもあり、シンクタンク研究員として地域社会に携わることの醍醐味を感じた。
さらに、顧客に提供する資料等の成果物に対する品質意識や日常的に顧客の高い期待に応じる必要性等、その道のプロとして業務を行うことの難しさを肌で痛感する。
その他にも公共施設に設定するネーミングライツ価格について学生時代に培った統計分析スキルを適用して新たに評価方法を検討する等、自身の経験値やスキルを実際の仕事に活かすことができ、学生時代と専門分野は異なっても普遍的なスキルとして業務への貢献が可能であることを認識できた。
この時期の主なアウトプット
- 観光施設の事業収支シミュレーション
- ネーミングライツ料の価格設定に関する評価手法の検討
- 業界雑誌への寄稿(官民協働事業の事業手法に関する制度解説)
研究員
自身の領域拡大の契機となる
入社以来、主に官民協働事業を主な領域として個別の公共施設の構想・計画策定や事業者公募支援等のアドバイザリー業務に携わってきたが、3年目以降は地域社会に対してより俯瞰的な視点から広域地方計画の策定や都市・地域戦略の検討に携わるようになる。
特に、地方創生の新たな施策としてデジタル等の新技術を活用した地域課題解決の必要性が叫ばれるようになったことを契機に、スマートシティの先進都市事例の調査や関連事業に従事する等、2年目までとは異なる新たな関係者との協働も含めて自身の領域を拡大する機会を得た。
これまでの業務でも自身の強みを活かせる場面は一定程度得られていたものの、スマートシティをはじめとした全国的な新たな政策の動きが自らの仕事を開拓する際の重要テーマのひとつとして登場し、コロナ禍による社会情勢の変化もあいまって自身としても当該領域について強い関心を持つことになった。
この時期の主なアウトプット
- 独立行政法人発注のスマートシティ先進事例調査業務のうち、ストックホルムの調査を担当し、紹介資料(公表物)を作成
- 内閣府のスーパーシティ事業について、自治体が国に応募する提案書(スーパーシティ構想)の作成を支援
研究員
次世代の地域づくりの検討に経験が活きる
5年目以降は業務の主担当者や実質的なプロジェクトリーダーとしてプロポーザルの企画書や業務成果物の作成、顧客対応を含むプロジェクト管理等に携わるようになる。そのようななか、特に施設計画やまちづくりの文脈では、当初に整備を予定した公共施設等についてコロナ禍によって施設のあり方や策定した構想・計画を改めて見直すこととなり、3〜4年目の頃に関与した業務のなかで得た次世代の都市・地域づくりに必要な新技術の活用等、新たな視点や考え方が、公共施設計画の見直しにおいても重要な検討事項の一部として効果的に活用された。
また、日々の打合せ資料や業務成果物等の作成においてはペーパーレス化やオンライン会議の拡がり等も意識してPCやタブレット端末等でより視認性の高い資料作成を意識する等、担当者として従来とは異なる新しさや変革を意識して業務に取り組んだ。
この時期の主なアウトプット
- ポストコロナ時代の庁舎のあり方を調査研究し、市庁舎整備の基本構想・基本計画の見直しを支援
- マイナンバーカードをテーマに当社発刊物『日本はこうなる』へ寄稿
副主任研究員
研究活動や学会発表経験が仕事の幅を広げる
7年目以降は副主任に昇格し、正式にプロジェクトリーダーとして案件受注やプロジェクト管理等に携わる。他方、入社5年目から業務の傍ら大学院博士課程に所属したことで、研究論文執筆等の業務外の稼働も徐々に高まり、業務で扱う案件数は絞りながら対応。
業務外の研究活動ではこれまでに業務経験を通じて得た自らの問題意識をもとに研究テーマを設定し、研究論文の作成や学会での成果発表を行ったほか、当社の自治体向けセミナーでも関連するテーマで発表を行う等、自身の研究内容を対外発信し、関連する領域で活動する人々と直接にコミュニケーションをとることで自らの偏りがちな思考や探究内容に一般性を持たせることに努めた。
また、博士研究で考察した内容はプロポーザルの企画書の作成等にも活かした結果、新規案件を受託する等、研究活動は業務にも間接的に良い効果をもたらした。
この時期の主なアウトプット
- 研究論文2件の学会発表(SDGsやスマートシティ等都市・地域マネジメントがテーマ)
- 博士論文を作成し学位を取得
- 令和6年度 当社地域政策セミナーでの発表(めざすまちを実現する施策とエビデンスのデザイン)
今後の展望
より現場に近いところから支援したい
今後の地域社会は人口減少の影響が本格化し、特に地方ではこれまで以上に多くの課題が表出すると考えている。そのため、シンクタンク研究員としての調査研究や政策提言に留まることなく、地域の課題解決や住民の暮らしやすさの向上に必要な取り組みの構築に貢献する等、ひとつでも多くの地域をより現場に近いところから支援していきたい。