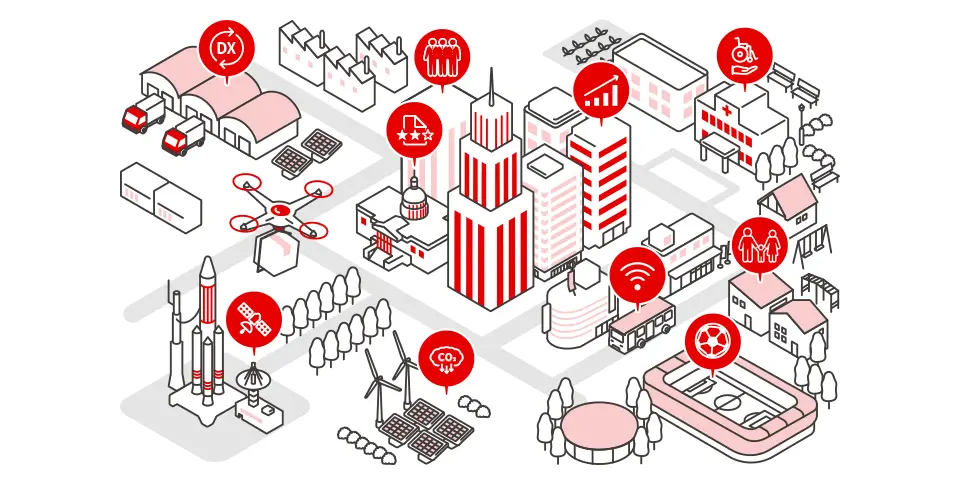制度利用者インタビュー

子どもの誕生にあわせ育児休職を利用。
復帰後も制度を活用して家庭と仕事を両立

子どもの誕生にあわせ育児休職を利用。
復帰後も制度を活用して家庭と仕事を両立
コンサルティング事業本部
社会共創ビジネスユニット グローバルコンサルティング部
マネージャー/2019年入社/創造理工学研究科 修了
自動車、通信、商社等業界を問わず、海外戦略、中期経営計画策定、販売戦略、新規事業立案等のプロジェクトに携わる。近年はグローバル×ESG・SDGs、地政学リスク領域のプロジェクトにも多数参画している。
制度の利用状況
子どもの誕生にあわせ、休暇や育児休職を組み合わせて2ヵ月間の育児のための休みをを取得。復帰後はテレワークを利用し、原則週3日程度は在宅勤務を行う。また、裁量労働制のため、平日18時~20時の間は基本的に予定をブロックし、育児・家事に専念。繁忙期は、その後の時間に勤務を再開する等、柔軟に調整をしながら仕事と家庭を両立している。
現在の仕事内容は?
幅広くクライアントを支援
日系企業の海外事業戦略や海外拠点管理、再編・撤退、中期経営計画策定、新規事業立案、ESG対応等幅広く案件を手がけています。近年は脱炭素や地政学リスク等のホットトピックを念頭に、海外事業戦略を検討するクライアントの支援を多数実施してきました。現在はマネージャーとして、生産プロジェクトのマネジメントだけでなく、案件の営業やセミナー講師、執筆等のパブリシティも担当しています。
制度利用のきっかけと活用方法は?
有給休暇と育児休職を利用
妻の妊娠が分かった直後から、社内ポータルで育児に関する支援制度を確認し、家族に共有しました。取得可能な制度を整理し、事前に人事部へ申請方法等を教えていただいたことで、スムーズに制度を利用することができました。
産前産後の家事・育児を家族で分担するため、休暇や育児休職を組み合わせて約2.5ヵ月の休みを取得。出産に確実に立ち合いたかったこともあり、出産予定日の1週間ほど前から有給休暇を組み合わせて休職を開始しました。

どのような働き方ができていますか?
育児・家事に集中する時間を確保
育児休職に入る3ヵ月ほど前に部内メンバー全員に周知し、以降のプロジェクトアサインを柔軟に調整してもらいました。
テレワークや裁量労働制は育児休職の前から活用していますが、上司やプロジェクトメンバーに配慮してもらい、平日夕方は育児・家事に集中するため会議を極力回避する等、上手くスケジュールの調整ができています。
クライアント訪問の予定を調整する際も、メンバーから可能な限り在宅前提で予定を確認される等、自身のライフステージを社内で認知してもらえていると感じています。
制度を利用してみて感じることは?
柔軟な働き方を可能にしてくれる
公的制度に加え、当社では育児休職の数日分を有給休暇扱いにできる制度があるため、収入減少をあまり気にすることなく、有給休暇も組合せて長く休むことができました。
テレワークや裁量労働制といった、当社ならではの自由な働き方ができるため、育児休職からの復帰後も以前と変わらずに仕事ができています。特に、テレワーク中心の勤務形態が許容されている点は、家族の急用や子どものトラブル時に柔軟に対応することができ、ありがたいと感じています。
ある一日の流れ
起床・朝の準備
普段は6時半に起床。妻と子どもが起きる前に、始業時間まで洗濯等の家事を片付ける。子どもの哺乳瓶やガーゼの交換は忘れずに行う。
始業
朝早くから始業することで、可能な限り夕方以降の業務量を減らしている。基本的にはクライアントや社内からのメールを確認し、優先度に応じて返信を行う。追って対応が必要なものは、TO DOリストとスケジュールに記入。また、このあとのミーティングに備え、ミーティング資料を再確認。議題の要点や論点を整理。
社内ミーティング
プロジェクトチームのミーティング。朝一にミーティングを入れることで、メリハリをつける意味がある。進行中の調査についての進捗報告と現状の課題点について議論。
昼食
在宅の場合は、妻が育児休職中のため家族全員で食事をとる。テレビを見ながら楽しく会話。子どもが高確率でぐずり始めるため、妻と交代でミルクをあげる。
出社
朝は在宅、午後は出社のパターンも多い。この日は午後にクライアント訪問が集中していたため、昼食後に電車で神谷町にあるオフィスへ出社。
報告会
プロジェクトメンバーとはこの後の報告会のすり合わせを行いながら、タクシーでクライアントへ訪問。プロジェクトリーダーとして冒頭あいさつをした後、メンバーが報告資料を説明。質疑応答時には後方支援を行い活発な議論を実施。
サテライトオフィス
クライアント先の最寄り駅にあるサテライトオフィスへ立ち寄り、30分×2回の社内ミーティングに参加。帰宅まで間に合わない場合は、頻繁にサテライトオフィスを活用。主要駅はほぼ拠点があるため、重宝している。
子どものお風呂・夕食
妻と一緒に子どもをお風呂に入れた後、ミルクをあげながら夕食。その日の子どもや仕事の会話をし、お互いの疲れを労う。
資料準備
その日の残タスクを片付ける。マネージャーに昇格してからは日中の会議も多く、繁忙期等は、資料作成を子どもの寝かしつけ後の夜の時間に集中して行うことも。
リラックスタイム
可能な限り、深夜残業はしない。入浴後、妻と雑談したり趣味のゲームをしたりする大切な自由時間。その後24:30くらいに就寝。
柔軟な働き方等を活用し、
子育てと研究員キャリアの両立を実現

柔軟な働き方等を活用し、
子育てと研究員キャリアの両立を実現
政策研究事業本部 東京本部 社会政策部
上席主任研究員/2003年入社/教養学部 卒業
2003年に当社へ新卒で入社。 2012年より2年間、内閣府男女共同参画局調査分析専門官として従事。2021年に管理職へ昇進し、社会政策部にてグループ長を務めるほか、当社の事業開拓組織である女性活躍推進・ダイバーシティマネジメント戦略室の室長として、同領域を専門に活躍している。また、亜細亜大学非常勤講師として、学生へのライフプランニング教育にも携わる。
制度の利用状況
2007年に出産し、育児休職を約2年間利用。復職後は、裁量労働制及びテレワークを活用し、育児と仕事を両立。管理職となった現在も週3日程度の在宅勤務を行っている。
現在の仕事内容は?
調査研究を担当
厚生労働省・内閣府等の委託調査を中心に、企業における多様な人材の活躍や、その土台となる多様な働き方に関する調査研究に従事しています。主な業務内容としては、調査等を通じて実態把握を行い、その結果を踏まえて官公庁の政策形成のベースとなる基礎資料の作成や政策提言を行っています。民間企業からのご依頼も多く、当社コンサルタントと一緒にコンサルティング案件にも携わっています。
受託業務以外では、当社独自の調査研究をもとにレポートを執筆したり、記事取材を受けたりと、さまざまな形で世の中に対する発信を行っています。また、大学の非常勤講師として、後期に週1回キャリア教育に関する講義も担当しています。
制度利用のきっかけと活用方法は?
ライフステージに合わせて働き方を調整
キャリアの大半を子育てと両立しながら働いてきましたが、裁量労働制やテレワーク等働く時間や場所を柔軟にできる制度は、責任のある仕事を担ううえでなくてはならないと感じます。当社では、研究員・コンサルタントはある程度経験を積めば裁量労働制が適用可能となりますし、テレワークについては誰もが利用できる制度として運用されているため、周囲に気兼ねすることなく自然と活用することができました。
加えて、政策研究事業本部にはある一定の年次になると社員が自分で給与を選択できる「選択年俸制」制度があり、年収に応じた年間の目標を設定することができます。これによって、働く時間に制約があっても、周囲の同僚等に負担をかけてしまうという心配を少なくできる点が特徴です。この制度を使い、ライフステージにあわせて仕事量を調整しながらも、毎年少しずつ上の役割にチャレンジしていくことを意識するようにしました。

現在は管理職とのことですが、どのように
子育てと仕事を両立してきたのでしょうか?
周囲のサポートによって責任ある役割を経験
裁量労働制やテレワークは、育児と両立しながらプロジェクト内での役割を果たすうえで、とても役立ちました。子どもが小さい頃は、日中働ける時間に制約がありましたが、繁忙期等仕事が残ってしまう時は、子どもが寝た後や早朝に自宅で仕事をすることもありました。また、テレワークも利用し柔軟な働き方をフルに活用してきました。
こうした制度を利用する際に意識したのは、職場のメンバーとのコミュニケーションです。予定を共有したり、大事な会議のときは万が一の際の代わりを先輩に依頼しておく等したりしました。そうした周囲のサポートのおかげで、子育て中でも仕事で責任のある役割を担い、リーダーの経験を積むことができました。今は子育て真っ最中の後輩に対して、自分がサポート役に回ることで恩返しできればと考えています。
制度を利用しながら働くことで、
どのような気づきがありましたか?
当社では育児と両立しやすい制度・環境を整備するとともに、本人が責任のある役割を果たせるよう、周囲によるサポートが自然に行われています。私自身も育児中は、限られた時間のなかでどうすれば自分の成長につながる経験ができるかを常に意識しながら、仕事の進め方を工夫しました。
育児等による時間制約は、キャリアの発展から見ればともすればマイナスに捉えがちですが、限られた時間のなかで成果を上げる働き方は誰にとっても必要なものです。制度を利用しながら働く期間は「仕事を計画する力」を養うことができる側面もあるのではないでしょうか。さらに、こうした経験が管理職になった今、メンバー一人ひとりの違いに向き合いながら、その成長を後押しすることにも役立っていると感じています。
ある一日の流れ
朝の準備
普段はだいたい6時前に起床。夫と日替わりでお弁当を作り、子どもと朝食を食べ、学校に送り出す。在宅勤務の日は始業時間までニュースを見たり家事をしたりして小休憩。
始業
クライアントや社内からのメール・チャットを確認。グループ長として、グループメンバーの日々の勤怠を確認。この後のミーティングに備え資料を再確認し、議題の要点や論点を整理。
クライアントとのミーティング(営業)
新規案件の引き合いがあったクライアントと、オンラインミーティング。仕様書について説明を聞き、見積り作成にあたって不明点やスケジュールを確認。
昼食・移動
この日は午前中が在宅勤務、午後からはクライアントとのミーティングのため、自宅で昼食をとり移動。
クライアントとミーティング
チームメンバーとクライアント先を訪問し、進行中の案件についてミーティング。調査結果について中間報告を行い、先方の問題意識を伺いながら今後の方向性について議論。
サテライトオフィスで作業
クライアント先近くのサテライトオフィスに立ち寄り、メール返信や調査業務を行う。メンバーから相談があれば、サテライトの会議室で、クイックにオンラインミーティングをすることも。
終業・帰宅
サテライトオフィスを出て帰宅。
夕食は、在宅との兼ね合いで夫と適宜分担。家族も帰宅し、一緒に食事をしながら学校や部活の様子等、一日の出来事を話す。ほっとするひととき。